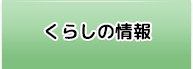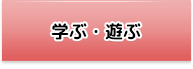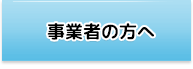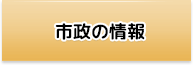介護サービスを利用するまでの流れ
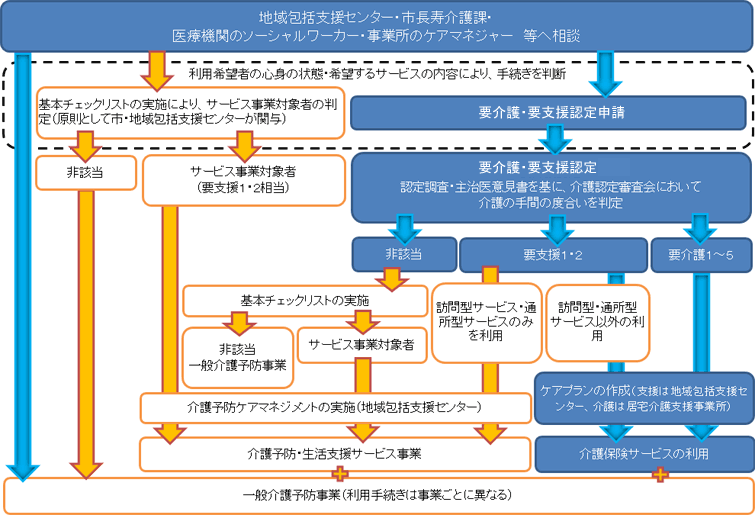
要介護・要支援認定申請
介護サービスを利用するためには、まず、要介護・要支援認定の申請が必要です。
介護サービスの利用を検討される場合は、市長寿介護課または地域包括支援センターへご相談ください。
(下記「地域包括支援センターとは」をご覧ください。)
対象となる方
①第1号被保険者(65歳以上の方)
②第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方で、特定疾病により介護が必要となった方)
申請の種類
①新規申請:要介護・要支援認定を初めて申請される方(有効期間が切れている方も含みます)
②更新申請:すでに要介護・要支援認定を受けている方が、有効期間内に再度申請する方
③区分変更申請:すでに要介護・要支援認定を受けている方で、心身の状況に変化がある場合に申請する方
申請窓口
市長寿介護課
認定申請日の取り扱い
要介護・要支援認定は、申請書を窓口に提出した日が申請日となります。申請書等を郵送した場合は、鳴門市が受理した日が申請日となります。
申請しようとする日が閉庁日であり、どうしてもその日に申請ができない場合は、事前にその旨をお伝えください。
更新申請について
更新申請は、認定有効期間終了日の60日前から満了日までの間に申請することができます。対象となる方には、事前に申請書を郵送いたします。
令和7年度 要介護更新認定・要支援更新認定 申請書 受付開始日[PDF:233KB]をご覧ください。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書(ここからダウンロードできます。)
- 介護保険被保険者証(ない場合には、「介護保険 被保険者証等再交付申請書」ここからダウンロードできます。)
- 40歳から64歳以下のかたは、医療保険被保険者証
- マイナンバー法関連の添付書類
(申請者により、添付書類が異なります。以下をご確認ください。)
①被保険者本人が申請する場合
・マイナンバーカード等の個人番号、本人確認ができるもの
②被保険者以外が申請する場合
・被保険者本人のマイナンバーカード等の個人番号が確認できるもの
・委任状((ここからダウンロードできます)
・申請者の本人確認ができるもの
※申請時、申請者の本人確認のために、マイナンバーカード、運転免許証等、顔写真のついているものは1点、公的医療保険証、年金手帳等顔写真のついていないものは2点をご提示ください。
※申請は、本人または家族、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設等の提出代行者が行うことができます。
※認定結果の通知は、原則として申請から30日以内におこなわれます。認定結果が出る前に、サービス利用を希望する場合は、担当の地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所へご相談ください。
地域包括支援センターとは
地域包括支援センターは、高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点として設置されています。鳴門市では、基幹型地域包括支援センターを1か所、生活圏域ごとに地域包括支援センターを5か所、設置しています。
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、高齢者ご本人、家族、地域の方々、ケアマネジャー等からの相談機関として、医療機関や介護サービス事業所等の関係機関と連携して問題の解決に努めます。
また、介護予防支援事業所として、要支援認定を受けた方の介護予防・サービス支援計画の作成を行います。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | FAX | 担当地区 |
|---|---|---|---|---|
| 鳴門市基幹型地域包括 支援センター |
徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜165-10
鳴門市産業福祉センター(うずしお会館)1階 |
088-615-1417 | 088-686-4059 | 市内全域 |
| 地域包括支援センター おおあさ |
徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57番地10 | 088-689-3738 | 088-689-3740 | 大麻町全域 |
| 地域包括支援センター 貴洋会 |
徳島県鳴門市撫養町立岩字五枚146番地 | 088-683-1075 | 088-683-1076 | 撫養町川東地区 (林崎・北浜・弁財天・岡崎・立岩) 里浦町全域 |
| 地域包括支援センター ひだまり |
徳島県鳴門市大津町矢倉字四ノ越5番地 | 088-686-1139 | 088-686-1179 | 大津町全域 撫養町木津地区 |
| 地域包括支援センター 緑会 |
徳島県鳴門市撫養町南浜字蛭子前東105番地 | 088-685-1555 | 088-685-8886 | 撫養町川西地区 (木津を除く。南浜・斎田・黒崎・大桑島・小桑島) 鳴門西地区 |
| 地域包括支援センター やまかみ |
徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂205番地の29 | 088-683-6727 | 088-683-6728 | 瀬戸町全域 北灘町全域 鳴門東地区 |
特定疾病
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は、特定疾病により介護や支援が必要になったとき、要介護・要支援認定を受け、サービスを利用することができます。
特定疾病とは、加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障害を起こす以下の疾病です。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護・要支援認定の手順
|
【訪問調査】
認定調査員が家庭等を訪問して、申請者や家族等にここ1か月くらいの「心身の状態」「介護や見守りの方法」「日常生活の状況」などについて動作の確認や聞き取りをします。 ※認定調査は生活の場において、原則平日の日中におこないます。 ※正確な調査をおこなうため、申請者の日頃の状況を把握しているかたの立会いをお願いします。 |
【主治医意見書】
市から申請者の主治医に意見書の作成を依頼します。 ※医療機関受診の際に、介護認定申請の意見書の記載について主治医にお伝えください。 |
 |
|
| 【一次判定(コンピューター判定)】 どの程度、介護の手間がかかるかを推計します。 |
|
 |
|
| 【二次判定(介護認定審査会)】 医療、保健・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で、認定調査票、主治医意見書をもとに、どのくらいの介護の手間が必要かを審査判定します。 |
|
 |
|
| 【認定】 介護を必要とする度合い(要介護状態区分)を認定します。 非該当、要支援1.2、要介護1~5 |
|
認定の有効期限
認定の有効期限は、原則として新規申請と区分変更申請等は6か月です。(状態の安定性により3か月~12か月の幅があります。)
引き続きサービスを利用するためには、更新申請の手続きをおこない認定を受けることが必要になります。更新申請の有効期間は3か月~48か月となります。
「おむつ代の医療費控除の証明について」
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などでおむつ代について医療費として申告することができます。
その場合、医療費控除の明細書の他に、「おむつ代に係る医療費控除確認書」か「おむつ使用証明書」を提出する必要があります。
市長寿介護課では「おむつ代に係る医療費控除確認書」の交付と医師が発行する「おむつ使用証明書」の様式の提供を行っております。
なお、令和5年以前に使用したおむつ代の申告については、取り扱いが異なっておりますので、詳しくは「令和5年以前の年分のおむつ代を申告する方」をご覧ください。
令和6年以降の年分のおむつ代を医療費控除する場合の必要書類
〇おむつ代に係る医療費控除確認書
市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して市長が交付するものです。ご希望の方は市長寿介護課に交付の申し出をしてください。おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。
1年目の方
主治医意見書が、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものであること。
※有効期間が連続しているものに限ります。
2年目以降の方
主治医意見書が、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものであること。
※前述の1年目の方、2年目以降の方のいずれにも該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際にかかりつけの医師が記載する「おむつ使用証明書」を提出していただくこととなります。
要件
①該当する年に要介護・要支援認定を受けていること。
②鳴門市が保有する介護認定に関する主治医意見書において、以下の2つの条件を満たしていることが確認できること。
「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること
「失禁の対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること
「おむつ代に係る医療費控除確認」の申出に必要なもの
- おむつ代に係る医療費控除確認申出書[DOC:38KB] おむつ代に係る医療費控除確認申出書[PDF:76.5KB]
- 本人の介護保険被保険者証
- 申出者(代理人)の確認ができるもの
- 本人の印鑑
令和5年以前の年分のおむつ代を医療費控除する場合の必要書類
令和5年以前の年分は、おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで申告の際に提出する書類が変わります。
1年目の方
〇おむつ使用証明書
はじめておむつ代の医療費控除を申告する場合に必要となります。
医師が記載するものですので、かかりつけの医療機関に以下の様式をお渡しください。
おむつ使用証明書[PDF:71.4KB]
2年目以降の方
〇おむつ代に係る医療費控除確認書
既に一度おむつ代の医療費控除を申告した方が2年目以降に申告する際に、医師による「おむつ使用証明書」の代わりとなるものであり、市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して市長が交付するものです。
ご希望の方は市長寿介護課に交付の申し出をしてください。
要件
①該当する年に要介護・要支援認定を受けていること。
②鳴門市が保有する介護認定に関する主治医意見書において、以下の2つの条件を満たしていることが確認できること。
「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること
「尿失禁の可能性」が「あり」と記載されていること
「おむつ代に係る医療費控除確認」の申出に必要なもの
- おむつ代に係る医療費控除確認申出書[DOC:36.5KB] おむつ代に係る医療費控除確認申出書[PDF:79.4KB]
- 本人の介護保険被保険者証
- 申出者(代理人)の確認ができるもの
- 本人の印鑑
サービスを利用するには
介護サービスを利用するには、個人にあったケアプラン、介護予防ケアプランの作成が必要です。
要介護1~5に認定された方(在宅サービスを利用する場合)
①ケアプランの作成を依頼
依頼する居宅介護支援事業所を選んで、ケアプランの作成を依頼します。
②ケアプランの作成
ケアマネジャーと面接し、アセスメントを受けて、ケアプランを作成してもら
います。
③サービス事業者と契約
④在宅サービスを利用
要介護1~5に認定された方(施設に入所・入居する場合)
①介護保険施設と契約
②ケアプランの作成
③施設サービスを利用
要支援1・2に認定された方(介護予防サービス利用の流れ)
①地域包括支援センターに連絡
お住まいの地区を担当する地域包括支援センターへ連絡します。
上記「地域包括支援センターとは」をご覧ください。
②地域包括支援センター職員との話し合い
職員がサービス内容を説明したり相談にのったりします。
③介護予防ケアプランの作成
支援メニューを作成します。
④介護予防サービスを利用
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード