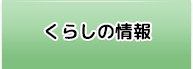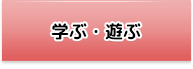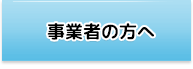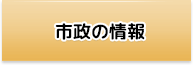障害児通所支援(障害児通所給付費)
児童発達支援・放課後等デイサービス利用ガイドブック
このガイドブックは、鳴門市自立支援協議会子ども支援部会で内容を検討し、通所サービスの利用を検討する際の一助になるよう、制度の概要や事業所の情報を取りまとめたものです。保護者の皆様はもちろん、保育・教育機関の皆様にもご活用いただけるものとなっております。また、サービスの利用の有無を問わず、切れ目のない支援ができるよう、相談先のページもありますので、是非一度ご覧ください。
児童発達支援・放課後等デイサービス利用ガイドブック[PDF:9.75MB]
障害児通所支援(障害児通所給付費)
障がい等のある児童に対して、下記の支援を行います。
| 児童発達支援 | 未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がいがあり、外出することが困難である障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 |
| 医療型児童発達支援 | 肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。 |
| 放課後等デイサービス | 就学中の障がい児等に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
| 保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
【申請から利用までの流れ】
|
1.申請・聞き取り |
鳴門市役所社会福祉課で申請と聞き取りを行います。 |
|
鳴門市社会福祉課 |
持ち物 |
|
2.意見書の提出 |
事業の利用が必要であることの意見書の提出が必要です。 □ 健康増進課(3か月以内に発達検査を受けた場合)の意見書 |
|
3.事業所を選ぶ |
ガイドブックを参考に、事業所に連絡の上見学など行い、 通所先を検討します。 |
|
4.計画を作成する |
目標や、利用頻度などを盛り込んだ計画案の提出が必要です。 |
|
※1.~4.の順番は前後しても大丈夫です |
|
 |
|
|
5.受給者証が届く |
障がい児通所受給者証には、利用者負担額、通所サービスの支給量、障がい児相談支援事業所などの情報が記載されています。受給者証が届いたら、利用する事業所に提出し、契約の上、通所サービスをご利用ください。 |
【利用者の負担額】
障害児通所支援を利用される際の利用者の負担金額は、原則として費用の1割となります。さらに、世帯全員に課税されている市民税の金額に応じて、利用者の負担する金額に上限を設定します。
| ひと月の利用負担上限金額 | |
| ①生活保護世帯 | 0円 |
| ②市民税が非課税の世帯 | 0円 |
| ③市民税が課税されている世帯(所得割の合計が28万円未満) | 4,600円 |
| ④市民税が課税されている世帯(所得割の合計が28万円以上) | 37,200円 |
※③と④の世帯が「児童発達支援」を利用する場合には、同一世帯に就学前の児童が2人以上いるか、世帯の所得が一定以下の場合には、利用者の負担金額を費用の1割から軽減できることがあります。
【就学前障がい児の発達支援無償化(国の制度)】
令和元年10月1日から就学前障がい児を対象とした下記サービスの利用者負担額が無償化されています。
対象となるサービス
児童発達支援 医療型児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援
対象となる期間
満3歳になって初めての4月1日から3年間
手続き
無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
※利用者負担額以外の費用(医療費や食費等、現在実費で負担しているもの)については、引き続きお支払いいただくことになります。
※幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
【就学前障がい児の発達支援無償化(鳴門市独自事業)】
令和5年4月1日から就学前障がい児を対象とした下記サービスの利用者負担額が無償化されています。
対象となるサービス
児童発達支援 医療型児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援
対象となる期間
利用開始時から満3歳になって初めての3月31日まで
※以降は、国の制度において無償化されます。
手続き
上記対象サービスを利用した際、利用した事業所に対して、所定の利用者負担額をいったんお支払いください(一月ごと)。
利用者負担額を支払った事業所より、領収書が発行されます。
上記の領収書と鳴門市児童発達支援等利用者負担額給付申請書(様式第1号)及び振込依頼書を社会福祉課にご提出いただきますと、ご指定の口座に翌月振り込まれます。
※振込口座は、通所受給者証に記載されている「通所給付決定保護者」名義のものに限ります。
※複数月分をまとめて、ご申請いただくことも可能ですが、お早めにご申請ください。
※利用者負担額以外の費用(医療費や食費等、現在実費で負担しているもの)については、引き続きお支払いいただくことになります。
【就学前障がい児の児童通所に係る利用者負担の多子軽減措置】
市民税課税世帯において、障がい児通所支援を利用している、または幼稚園等に通う児童が2人以上いる場合、障がい児通所支援を利用する就学前の第2子以降の児童について利用者負担が軽減されます。(放課後等デイサービスは対象外です。)
軽減対象の判定について
世帯の市町村民税所得割合算額と、兄・姉の数によって軽減を判定します。
軽減後の利用者負担額
| 区 分 | 軽減判定 | |||||
| 小学校就学後児童 | 軽減対象外 | |||||
| 就学前児童 | 世帯の市町村民税所得割 合算額が77,101円未満 |
生計を同じくする兄または姉がいない | 軽減対象外 | |||
| 生計を同じくする兄または姉がいる | 第2子軽減 | |||||
| 生計を同じくする兄または姉が2人以上いる | 第3子以降軽減 | |||||
| 世帯の市町村民税所得割 合算額が77,101円以上 |
障がい児通所支援または幼稚園等に通う 就学前の兄または姉がいない |
軽減対象外 | ||||
| 障がい児通所支援または幼稚園等に通う 就学前の兄または姉が1人いる |
第2子軽減 | |||||
| 障がい児通所支援または幼稚園等に通う 就学前の兄または姉が2人以上いる |
第3子以降軽減 | |||||
次の(1)から(3)までの額を合算した額と受給者証記載の負担上限月額を比較し、低い方の金額が利用者負担額となります。
| (1)軽減対象外の児童 | サービスにかかる総費用額の100分の10 |
| (2)第2子軽減対象児童 | サービスにかかる総費用額の100分の5 |
| (3)第3子以降軽減対象児童 | 0円 |
手続き
- 所得割合算額が77,101円未満の世帯:兄または姉の通園(通所)証明書
- 所得割合算額が77,101円以上の世帯:住民基本台帳上、同一世帯に兄または姉がいることが確認できる場合は証明書等の提出は不要です。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード