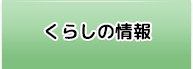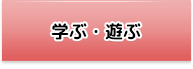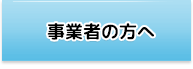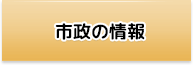補装具費の支給
補装具とは
障がい者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるもの等。補聴器、義肢、装具、車椅子、電動車椅子等があります。支給対象者は身体障害者手帳の所持者です。
補装具費の支給
補装具費の支給をいたします。利用者負担については、原則として1割を利用者が負担することとなります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。
支給決定は、障がい者又は障がい児の保護者からの申請に基づき、市が行います。
なお、65歳以上の方については、車椅子、歩行器、歩行補助杖等は、原則、介護保険制度の給付が優先となります。介護保険の給付対象とならない方は補装具費支給の対象となります。
補装具費の支給の仕組み
補装具の種類によっては申請時に指定医による意見書が必要な場合があります。
- 申請者が市へ補装具費支給申請
市から更生相談所等(指定自立支援医療機関)へ意見照会、判定依頼
捕装具によっては、直接県障がい者相談支援センターの判定を受けていただいたり、意見書が必要な場合があります。 - 市が補装具費支給決定(種目・金額)
交付に必要な決定通知等の書類を送付いたします。 - 利用者と補装具製作(販売)業者が契約
更生相談所等(指定自立支援医療機関)から補装具製作(販売)業者へ製作指導、適合判定 - 補装具製作(販売)業者から利用者へ製品の引渡し
- 利用者が補装具製作(販売)業者へ補装具の購入(修理)費支払い(100/100)
- 利用者が市に補装具費支払いの請求(90/100)
- 市から利用者へ補装具費の支給
なお、別途、市で設ける代理受領方式による補装具費の請求・支払いも可能です。
補装具費支給制度の利用者負担
補装具費支給制度の利用者負担は、原則として定率(1割)となっています。
ただし、世帯の所得に応じて下記の負担上限月額が設定されます。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市民税非課税 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は、障がい児(18歳未満)は世帯全体、障がい者(18歳以上)は本人と配偶者が原則ですが、住民票で同じ世帯となっていても税制と医療保険で被扶養者でなければ、 障がいのある方とその配偶者を別世帯の扱いとすることができます。
また、こうした負担軽減措置を講じても、定率負担をすることにより、生活保護の対象となる場合には、 生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額を引き下げます。
なお、世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。
ただし、令和6年4月1日から、障がい児に対する所得制限が撤廃されたため、障がい児については、世帯の所得に関わりなく、補装具費の支給対象とします。